言葉にできることと、できないことがある。
ちょっと前までは、うまく言葉にできないことにうまいこと枠組みを与えて伝えることができるのが文章の上手な人だと思ってたんだけど、最近は言葉にできないことは言葉にしないままに、その存在を伝えることができる人が文章の上手な人なんだと思うようになりました。
具体的にと言われてもそれこそ言葉にできないというか、漠然とした印象でしかないのでこんな曖昧なことしか言えないのが心苦しいのだけど、「言ってない」、「目に見えない」、「誰も知らない」、だけどその存在のことはなんとなく分かってしまうという文章に触れたとき、「ほぉー」って思う。
そういう文章が書けるようになりたいなあ。書いてないのに伝わること、言ってないのにそれがあると信じてしまうこと。
Contents
すごい文章とダークマター
しょっぱなから主張を覆すようだけど、この感じをどうにかして伝えたいと考えていたら、「宇宙」を例に出すのが一番分かりやすいのではないかなと思いました。
宇宙には星がたくさんあります。
夜空を見上げれば無数の星が見えますが、僕らの肉眼で把握できる星の量はたかが知れていて、宇宙空間には僕らの想像をはるかにこえる空間が広がっています。
宇宙空間に多数存在する星も物理法則に支配されているはずですから、計算でその重さを知ることができます。
ちなみに僕は物理学にも宇宙科学にも詳しくないので適当に聞いてください。
どうやら宇宙に存在する物の質量は計算ができるようなのです。
しかし、その計算がどうしても合わない。理論上こうなるはずだという計算結果と、実際にその対象を見て計算したときの結果が合わない。
ということは、観測できないけど「質量に影響を及ぼす何か」があるに違いない。
その何かが「暗黒物質」とか「ダークマター」って名付けられた物質で、これは観測できないという意味では無いんだけど、物理に影響を及ぼしているという意味では在るんです。
しかも「ちょっとある」わけじゃなくて「けっこうないと計算合わなくない?」というものなんだから物理学者は困ってしまうのだそうです。
教える文章、悩ませる文章
宇宙科学や物理学の話をしたいのではなくて、あくまで言葉、言うなれば言語学の話をしたいのです。
ダークマターは例だけど、言葉の領域にも、言葉にできるもの(観測できるもの)と言葉にできないもの(観測できないもの)がある。
ところで、宇宙のなかにどうやら何かあるらしいぞという物質については「ダークマター」なんて名前が付けられてしまいましたから、その物質の概念を言葉によって固定されたことになります。
誰も見たことがないし、よく分からないのに、「ダークマター」と言えば「はいはいアレね」ってみんなが分かるようになる。これは明らかに物理の力ではなく言語の力ですよね。
だから本来、言葉にできないこと、よく分からないことに輪郭を付けて、人に渡せるようにするという作用が言葉にはあって、それが上手にできる人が「言語」や「文章」の上手な人だと思っていたけど、そういう道具的な域を超えて、みんなに「ん、なんかあるんじゃない?」「見えないところに絶対何かあるよ!」って思わせる文章を書く人の方がすごいなと思ったという話です。
だってそれは「よく分からないものを説明して教えてる」んじゃなくて、相手の中に「説明しえない何かの存在」を植え付けてるんだから。
前者が「分からないを分かった」に変える手段だとすれば、後者は「分からないの分からなさを共有する」手段。
書くという行為が作業になるか創造になるかの差はここにあると思うし、個人的には後者の能力の方に憧れる。そっちの方が断然難しいと思うから。
僕はこういう風に良い文章から遠ざかる
ただ、だからと言って「行間を読む」とか「含みを持たせる」とか「あえて言わない」とかそういう小賢しげなレトリックのことを言いたいわけではないです(いやレトリックは大事だけども)。
最初に宇宙やダークマターを例に出したのは、ここのところをもっとうまく「説明したい」と思ったから。
ここで言っているのは、「ただ無い」のではないし「ただ在る」のでもない。
「ただ書く」とか「ただ書かない」のでもないということ。
直接それを見ようとすればその存在のことは全然分からないし分からないゆえに「無い」と言わざるをえないのに、それ以外の「在る」ものを眺めたときに「無きゃおかしい」と思われる何かが生まれるという不思議を話したいのです。
言えば言うほど意味が分からなくなりそうだけど、「明らかに在るものを見たときにだけ分かる非存在の存在」ってのが、言葉にもあるよねって言いたい。
「行間を読む」とかそういう話じゃないんよって言ってるのは、「行間」っていうものを意識した瞬間に概念として存在してしまうから。
「ダークマターってのがあって…」って話すとダークマターの存在が分かってしまうように、「言葉にできないこと」に適当な名前を与えてしまうととりあえずそれがあることが分かってしまう。
誰かの理解を促したいのではなく、分からないものの存在を共有したいのです。
だけどこんな風にある程度理屈を並べてみても、そのゴールには至りません。
「分からないものの存在を共有したい」という気持ちは伝わったとしても、「分からないものの存在」そのものについてを伝えることはできない。
書く力が足りないのです。
もしくは神様の存在
非存在の存在という意味では「神様」を引き合いに出しても良いかもしれません。
目に見えないし多分いないけど、いないと説明ができないことが僕ら生きているとよくある。
僕らの周りには常に神様がいる。宇宙には多分いる。森の中や海の底にもいるだけでなく、都会の喧騒の中やトイレにまでいると言います。
もしくは「今自分がいる場所」に自分がいるのは神様の采配かもしれないし、誰と会うか、何をするか、喜び悲しみ怒りといったすべての感情の隅々にまで神の力は影響しているのかもしれません。
たまにそういうことがある。そうじゃないと理屈に合わないこと。目に見えない何かで繋がってないと、とてもとても納得できないこと。
いくら満天の夜でもやはり空隙の方が多いように、目に見えるもの手に取れるもの説明できるものをいくら並べても常にその間には絶対に「何か」があって、僕らはそれらに「神様」って名前を付けてしまうことがある。
埋め尽くそうとしてはじめて感じる質量
逆に言えば、文章を書くときは「ダークマター」や「神様」の存在を許さないという態度で、空間を埋め尽くすように言葉を使わなければならないと思います。
星空を見てみれば星は空に満ちているし、それぞれあらん限りの輝きを放っています。それに夜空を見るときは誰でも当たり前に「星」を見るはずで、例え目に見えるもの以外のダークマターみたいなものに思いを馳せることはあっても「主は星」であることに違いはありません。
言葉にできないことを伝えたいと思っても、「それ在りき」で筆を進めるとそれは目に見えないままなんじゃないか。
確実に在るものを精一杯ならべて、その上で浮き上がってくる非存在こそが、「説明できない質量」となって僕らの前に現れる。
ゴタクは良いけどお前が言うすごい文章ってなんやねん、と思われた方のために参考文献を挙げるとすれば、まず『青が破れる』。これは良い。とても憧れた。
 |
![]() 最近出た本ですね。10月に文藝で読んで感動したのですが、図書館で読んだため泣くに泣けず、単行本が出てたので買って読みました。
最近出た本ですね。10月に文藝で読んで感動したのですが、図書館で読んだため泣くに泣けず、単行本が出てたので買って読みました。
ちなみに、体感で言えばこの単行本、文字がやたらでかく感じました。薄くても良いから絶対もう何ポイントか小さい方が良いと思う。一文一文に贅肉がないのに二行になってしまってる箇所が多いのは地味にストレスだった。
よって電子書籍の方がおススメ(ポイント変えれるよね?)。上のリンクはkindleバージョンです。近くに文藝が置いてある図書館があるならそっちで読むのがベスト。字が詰まってる。それか文庫になるの待つか。
すごい文章を読めば感じる、見かけ以上の質量について。(完)


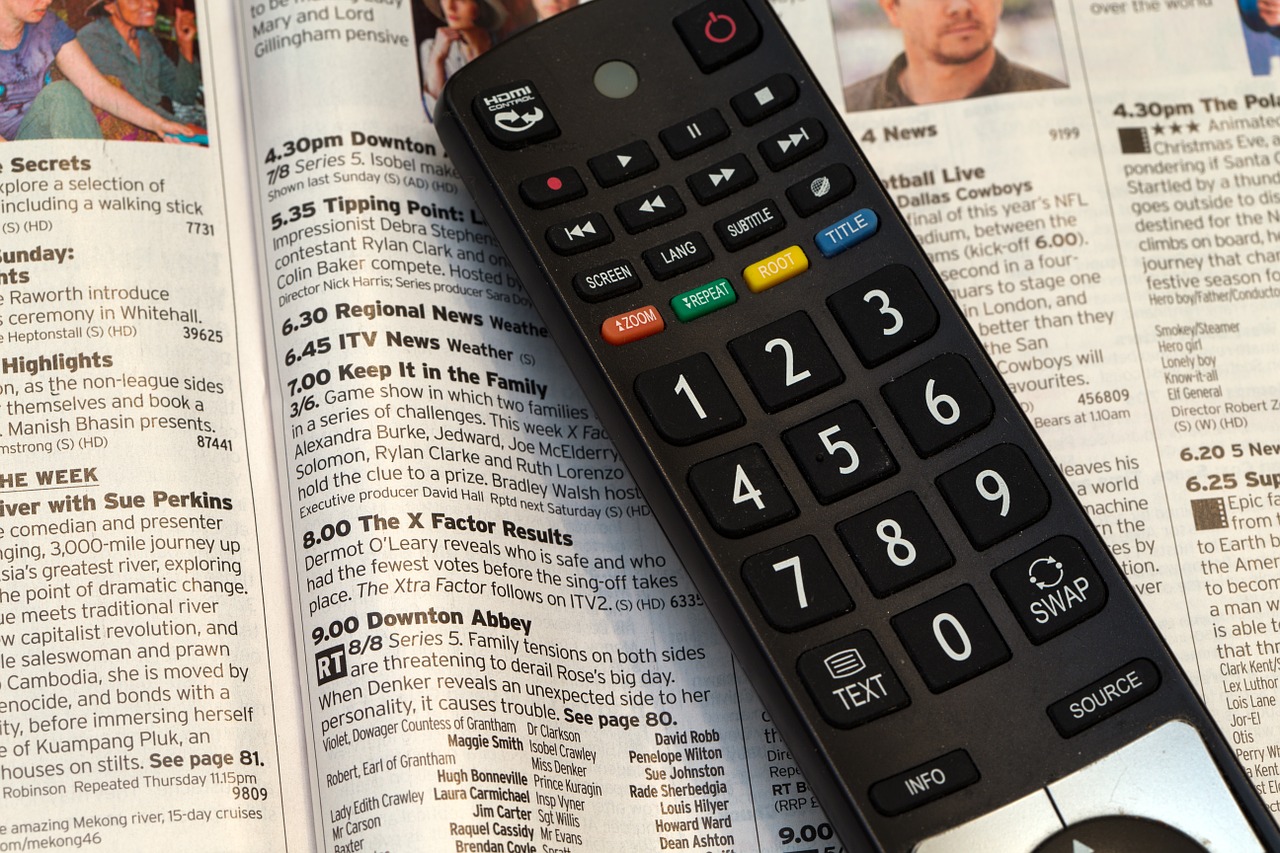
コメント