僕が小説を書くきっかけとなった保坂和志著『書きあぐねている人のための小説入門』の中に以下のような文があります。
「小説を書く」とは「小説とは何か?」を考えることだ、とくり返してきた。
しかし、それは、四六時中、小説のことばかり考えるという意味ではない。私自身の例で言うなら、小説を書きだす前は、ジャズやロック、現代音楽など、音楽のことを考える時間がとても長かった。理由は、最初のうちはもちろんそういう音楽が好きだったからだが、小説を真剣に書こうと思い始めた頃から、音楽を聴いたり、音楽について考えることが、そのまま小説のことを考えることになった。
保坂和志 『書きあぐねている人のための小説入門』38pより
僕の場合、「まちのことを考えること」がそのまま小説を考えることになっている気がします。
だからこのブログはすべて小説のことを考え積み上げてきた記録と言って過言ではありません。
もちろん最初そのつもりはなく、自然に自分の故郷、田舎について考えていたのだけど、自然と「小説」という形式に収束していくという印象。
その感覚を持って引用した保坂和志の文を読むと、言っていることがよく分かる気がしました。
小説のネタにする、のではなく、小説以外を考えながら小説に行きつく
もう少し、先ほど引用した文の続きも引用させてください。
これは、音楽を小説のメタファーにしたり、音楽を小説に置き換えたりするということではない。音楽のことを考えるのと並行するように小説のことも考えているという言い方をしてもいいけれど、大事なのは音楽なら音楽を簡単に小説のヒントにしようなどとは考えないことで、音楽は音楽として考える。そうしているうちに、「表現」ということにまで考えが伸びていき、それが結果的に小説を考えることにもなっていく。
これ、とても重要だと思います。小説という表現を志す人はつい、「これは小説に書けるんじゃないか?」「これは小説のネタになるんじゃないか?」という風に考えてしまうと思います。
嫌なことがあったら、「この経験もいつかネタになるだろう」と思ったり、仕事や家事をしているときなんかも脳内で小説の形に、見たこと、感じたことすべて変換して記録していないでしょうか。
重要なトレーニングだと思う一方で、それは既に知っている「小説」を考えているのであって「自分の小説」のことを考えているわけではないと思うのです。
まちづくりブログと小説
微妙な差ではあるけれど、「まちづくり」や「いなかまち」を小説の舞台にしようとか、地域のあるあるを小説に盛りこもうと考えるのと、「まち」の未来や過去や今、そして実際に生活し、嫌になっちゃうことしきりの毎日の中で「小説」という表現に行きつくのとでは、出来上がるものが違うと思う。
『書きあぐねている人のための小説入門』は僕にとって親のような存在で、何度も参照しているから、ただそう思いたいだけなのかもしれません。自分のことは否定したくないですからね。
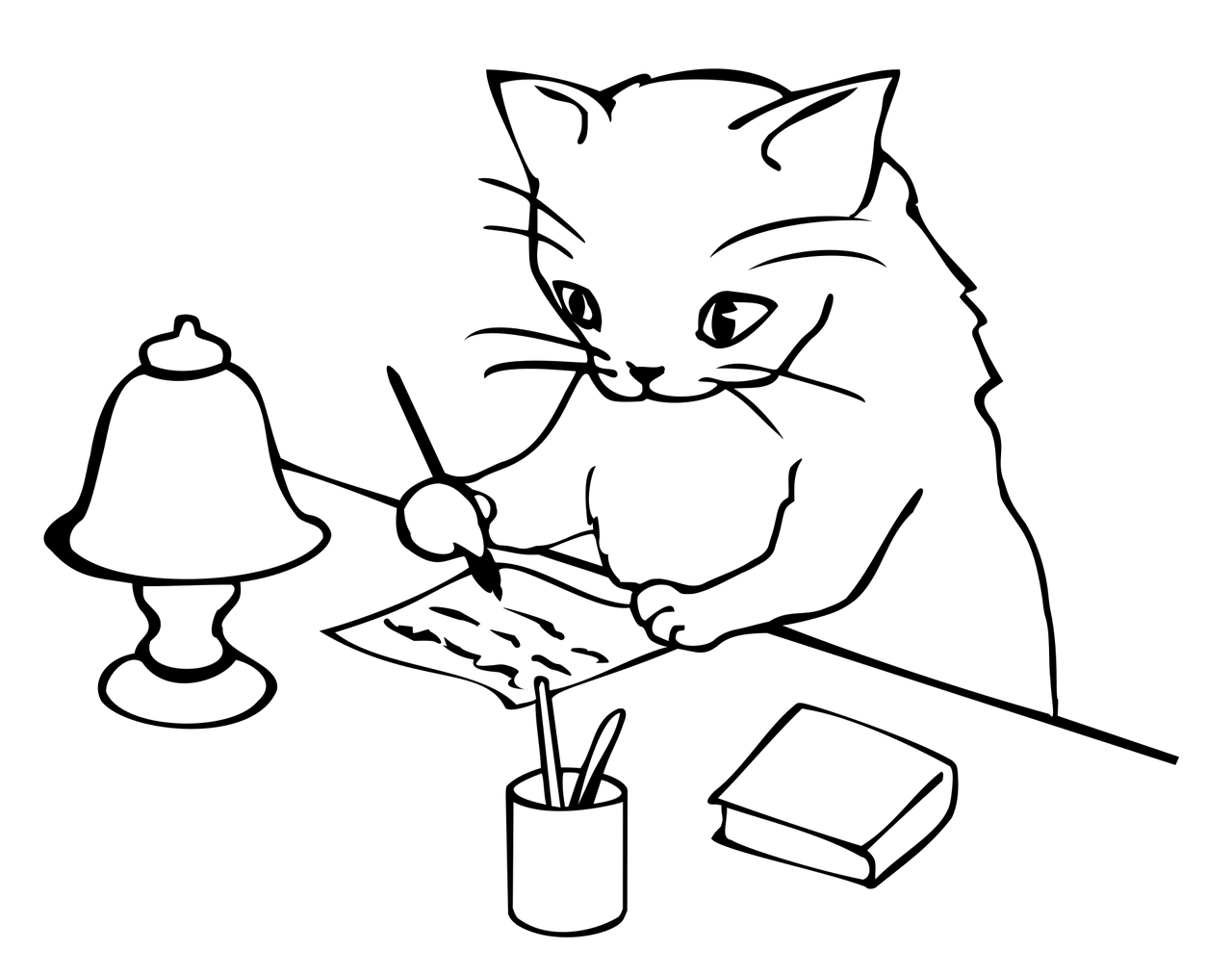
小説を書くと言いつつ「まち」のことばかり考えている自分を否定したくないばかりに、都合の良い引用をしているのかもしれません。
しかし本当に、最近ようやく、僕なりの表現の仕方みたいなものの輪郭が見えてきた気がしています。ブログを書き始めて、つまり「まち」のことを考えはじめて約5年。やっと輪郭ですが、「小説」に行きつくのは面白い。
何が小説に行きついても良い
余談だけど、作家には昔バンドをやっていたとか、音楽に造詣が深い人がけっこう多い印象です。
文学(小説での言語表現)と音楽の親和性に注目した上で比べてみた文章を過去に書きましたので暇な方はどうぞ。

また、現在読んでいる町屋良平著『ショパンゾンビ・コンテスタント』という小説では、音大に入りピアノの道を志していたが途中で挫折して今は小説を書いているという男性が主人公です。
まだ読んでいる途中なので確かではないけれど、彼もまた音楽をしている間ずっと、もしくは恋や友情を通してずっと、「小説」を考えていた人なのではないかと思います。
だからきっと、生来的に「小説」を書く人ならば、今考えていること、今真剣なこと、もしくは過去に真剣だったことが自然に「小説」に向かっていくのではないでしょうか。





コメント