小説を書くつもりの頭で書く文章は、小説っぽくなる。
小説モードの頭で「言葉を紡げば」、小説らしきものができあがる。
それを、例えばWEB上で公開すれば、小説を読むつもりの人がその小説を読む。
この両者に食い違いはなくて、むしろかっちり噛みあって、その文章は「小説」として存在するようになる。
小説を書くつもりで書く人と、小説を読むつもりで読む人が、ある種の小説を作ってる。
書き手と読み手の相互的なやりとりによる、手続き的な小説。「小説らしきもの」であればあるほど小説になれる小説。
小説家じゃない人の小説は、そういう風にかろうじて成り立っている。
この、「ある種の小説」もしくは「手続き的な小説」が作られる地場は心地よいけれど、心地よいからこそ脱却を図らねばならぬ。
小説モードになる頭をトンカチでぶったたけ
「ある種の小説」が作られる地場は心地よいです。
安心感があるからです。
小説を書いたと宣言し、そうか、それなら小説を読もうかなと思う人がそれを読むことで、とりあえず、一応は「小説」として存在できる。
「こんなのは小説じゃない」と言ってみたところで、読み手と書き手の間で間違いなく「小説」という認識が既に出来上がっているので、偏屈な人にしか見えない。
この記事を書いている背景には、このブログでよく引き合いに出す小坂一志著『書きあぐねている人のための小説入門』の中に「頭を小説モードにしない」という章の存在があります。
-前略-
たとえば言葉づかいひとつとっても、投稿小説ではふだん自分が使っている言葉ではなく、小説用の言葉を使っているものが非常に多い。-中略-
その結果、どこかで読んだような、きわめてステレオタイプな小説が出来上がってしまうわけだが、書いている本人はそうでないと小説ではないと思っている。つまり、小説の外見に守られることで、小説を書いているつもりになっている。
-中略-
‘‘小説言葉‘‘を使ったら、その小説は、小説でなく、すでにあるものになってしまう。
保坂和志『書きあぐねている人のための小説入門』174~175p
これは素人、プロ問わず小説を書くすべての人が考えなければならないことだと思うけれど、「とりあえず小説が書けて」「とりあえず小説と思ってもらえる」ような磁場がある環境(WEB上だとか)ではより強く意識しなければならないことだと思います。
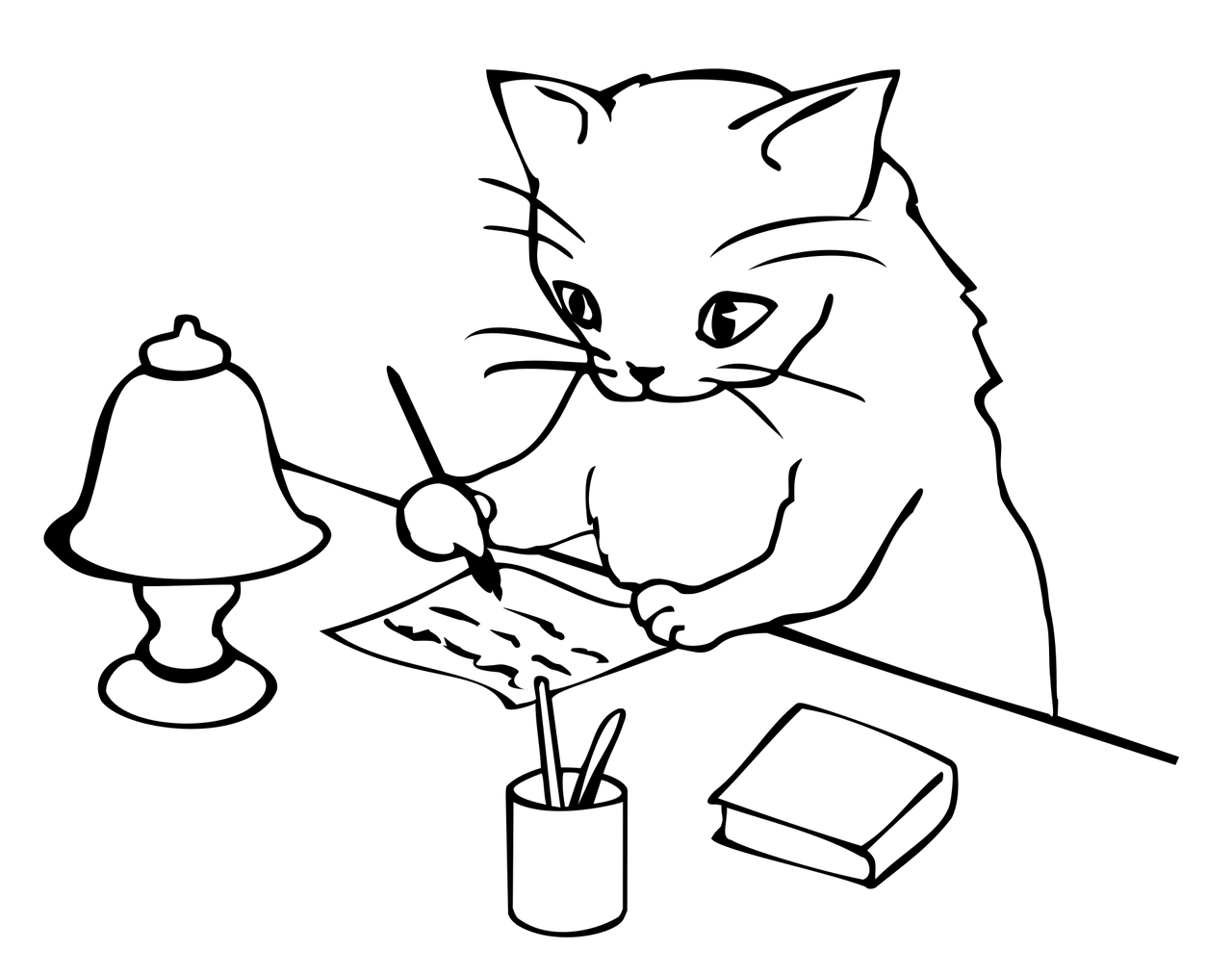
それは良く見たら塗り絵でした
上で引用したような文章を読んでいたにも関わらず、「頭が小説モードになっている」という自覚があるにも関わらず、頑張って小説らしきものをしばらく書いていたような気がします。
小説を書いた、これは小説です、と宣言するだけでとりあえず小説になってしまうような場所で書いた。小説の表面をなぞるだけで、こうしてブログを書くような気楽さで、今日一本書くか、なんてノリで、小説を書いていました。
それが虚しいというか、もどかしい気持ちになって、ちゃんと小説を書きたいなあと思うようになりました。
これまで書いたものにもところどころ「真実」とか「切実」とか、そういうものが書けた部分があるけれど、どうしても小説をなぞる作業にしかならなかった。
自分らしい絵を描こうと思っているのに、それは良く見たら塗り絵でした、という感じ。
輪郭はうっすら見えていて、どんな色彩を選ぶかもやんわり決められているようなものでした。
それじゃダメです。僕は僕の創作的な好奇心も冒険心も満たすことができず、作業を繰り返すだけになってしまうと感じました。


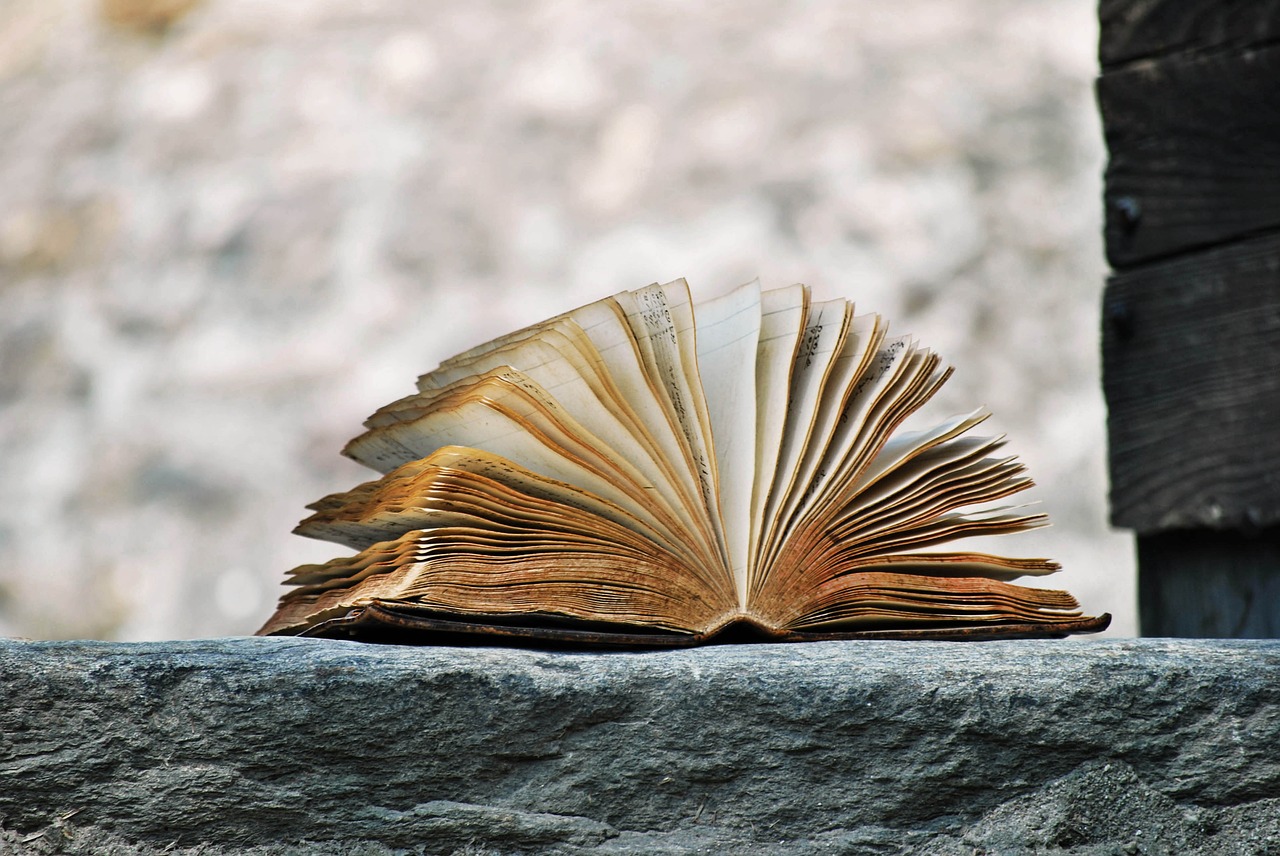
コメント