なにかと「枠にとらわれない」ことが良しとされることが多いです。
現状打破、斬新なアイディアの発想、マンネリの解消などなど、日常の問題をクリエイティブに解決する手法の一つとして、多くの心の中に「枠にとらわれない」というキーワードがあるのではないか。
対して、一般に「枠にとらわれる」のはマイナスの出来事、と見なされます。
しかし、問題は意識しないまま枠にとらわれることであって、実際には「枠」を強く意識することを求められる機会は多いのではないでしょうか。
例えば、ある文学賞に応募しようと思ったらその賞の傾向や、求められている作風をよく吟味して創作に当たるのが普通です。
何らかのテーマが定められている絵画や写真のコンテストではそれに沿う必要があるし、イベントやプロジェクトの企画を発想する際はまずどんな「枠」なのかを理解しなければならないと思います。
「枠」。「枠」の話です。
媒体、額縁、プラットフォーム、テーマ、舞台、リング、などなど。内容を包み込むものをどう見なすか、みたいなことを考えたいと思います。

「枠にとらわれない」と「枠をとらえる」
少し細かい話になりますが、枠がどんなものなのか掌握しないままに思考が硬直化している状態だからこそ「とらわれる」と表現されるのだと思います。
「枠」そのものにマイナスの意味が込められているのではなく、「とらわれている」のがマイナス要素なんですよね。
とても受動的で、身動きが取れず、抜け出せない状態だからこそ「とらわれる」わけです。
よって、ときたま「枠」そのものを忌避対象とする人や、定型的なものを無暗に馬鹿にする人がいますが、それは決して賢い態度とは言えないと思います。
枠を檻や枷と見間違えて、ただ自由を制限されていると感じるのは被害妄想的であり、「枠にとらわれない」ことにばかり注意を注ぐのもまた「枠にとらわれた」状況なのかもしれません。
僕ら適宜「枠をとらえる」ことが大事なんですよね。
なんのために枠をとらえるのか
枠をとらえるのが大事。
しかし、枠をとらえるのが大事、と唱えていては飽和やマンネリの温床になってしまう。
なんのために枠をとらえるのかを自問自答すべきなんだと思います。
目的は大きく二つ考えられます。
少し枠からはみ出して、つまり枠にとらわれないながらも驚きや違和感、感動と言ったものを作り出すため。
一つは、枠の中に収まるべきものの中で足りない分を補ったり、より枠を補強・増幅させたりするため。
枠を意識することは目的ではなく、手段としなければならない。
「枠にとらわれない」という言葉を呪文やお題目のように口にしても、結果的にただ奇をてらったようにしか見られなかったり、まったく無視されてしまったりすることが多いと思います。
一方、枠をとらえて、それだけで満足していては驚きや感動を与えることが難しくなる。
だからなんのために枠をとらえるのかを問う必要があると思うけど、これが難しいですよね本当に。

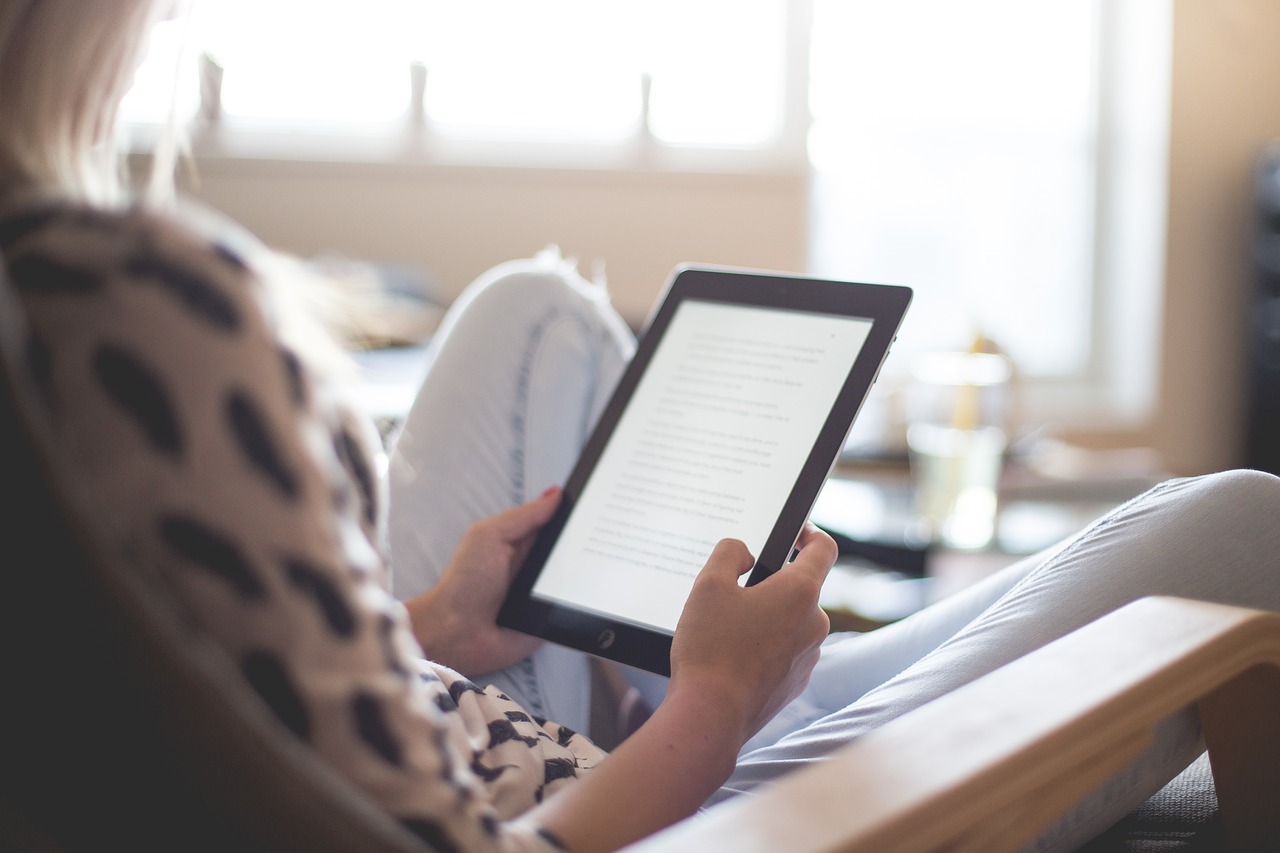
コメント